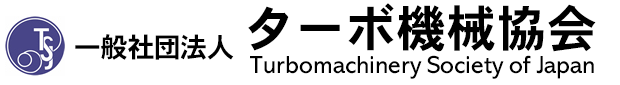2024年度(第15期)事業報告
(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
【事業活動の概要】
一般社団法人ターボ機械協会(以下、本会)は1,000名近くの正会員、学生会員と約150社の特別会員を擁する、プロフェッショナル集団です。本会は、産官学が一体となって、新規技術の適用可能性の調査研究や情報共有を図ることを目的とした調査研究事業(分科会活動)、雑誌「ターボ機械」の発行、規格・規準の取り纏め、国際誌「International Journal of Fluids Machinery and Systems(IJFMS)」に対する編集協力などの出版事業、総会講演会・地方講演会・国際会議の開催などの集会事業、各種セミナーや交流会の開催をとおした啓蒙・啓発事業、畠山賞・小宮賞の贈呈などの表彰事業、および、会員にとって有益な情報を提供する会員サービス事業を主な事業として活動をしています。
本会の総会、理事会、講演会、セミナー、CPD講座、講習会、委員会・分科会などの事業活動は、従来通りの活動を継続しています。オンサイト開催を基本に、オンラインシステムも併用した運営を実施し参加者の増加に貢献しております。
予算に関して、当初予算では1,756千円を見込んでいた当期収支差額は約585千円の赤字となる見込みです。これは、個人会員受取会費の4,724千円(2024年度分)、962千円(2023年度分)の未回収、特別会員受取会費の未回収718千円、シンポジウム講習会費,出版会費の2,555千円の増収などの結果となります。個人会員の受取会費の回収は喫緊の課題であり早急な対策により収支の改善を検討します。本会の最大の懸案事項である会員数の減少に関しては、本年度当初の正会員+学生会員数876名に対して、年度末会員数は861名+トライアル会員数17名となっており、若干減少傾向にあります。会員増強に関しては、引き続きイノベーション推進委員会などで対策の協議を継続していきます。
本年度は、上記のように各種事業を予定通り実施できた結果、会費受け取りの遅延による財務の悪化と会員数減少の傾向をある程度緩和することができたと認識しております。
以下、項目別に2024年度の事業活動の概要を報告いたします。
(1)調査研究事業(委員会・分科会活動)
現在、協会には水力機械委員会の下に7分科会(水車分科会、キャビテーション研究分科会、ターボポンプ分科会、水力エネルギー分科会、ポンプ吸込水槽模型試験法の調査・研究分科会、海洋ターボ機械技術開発分科会、プロペラ分科会)、空気機械委員会の下に2分科会(可変速(VSD)モーター駆動回転機械の諸問題検討分科会、送風機・圧縮機の騒音と性能研究分科会)、蒸気機械委員会の下に1分科会(蒸気タービン技術向上分科会)が常設分科会それぞれ設置されています。これらの常設分科会は、水力機械、空気機械、および蒸気機械のそれぞれの機械に関連した調査研究や情報共有を図ることを主たる目的として活動していますが、総務理事会の下に設置されている、トライボロジー研究分科会、ロータダイナミクス研究分科会、生産技術研究分科会、過給エンジンシステム分科会および多領域ダイナミクス設計研究分科会の5つの分科会では、横串を通す基盤技術に関する情報共有を図っています。また、活発な活動を実施してきた流体性能の高精度予測と革新的流体設計分科会は2024年7月に最終成果報告書の提出で終了いたしましたが、その後継分科会としてターボ機械および船舶分野における次世代計算技術の実用化推進分科会が発足しました。また、カーボンニュートラル社会の実現のために早急に社会実装を実現する必要がある液体水素などを用いる流体機械、流体機器の課題解決、開発支援のために極低温流体基盤・応用技術研究分科会が発足し活発な活動を開始いたしました。ターボ機械に関するプロフェッショナル集団として、分科会活動を更に活性化して行くため、新設あるいは改編などの討議を継続して行きたいと考えています。
(2)出版事業
雑誌「ターボ機械」52巻第4号(2024年4月号発行)から53巻第3号(2025年3月発行)の12冊を編集・発行しました。
(3)集会事業
ア. 総会講演会
2024年5月17日、第90回総会講演会を早稲田大学西早稲田キャンパスにて開催いたしました。元当協会会長の加藤千幸先生(日本大学)に「ターボ機械のCFDの現状と今後の展望 ~40年余りの開発と応用の経験から~」と題する特別講演をしていただきました。
第35回 小宮助成金受賞者講演として、筑波大学の金川哲也先生により「気泡流中を伝わる圧力波の非線形発展を利用したポンプ内水管の保守管理のための基盤理論創成と技術開発」、第33回 畠山助成金受賞者講演として佐賀大学の木上洋一先生により「潮流発電用の往復流型集流装置付きタービンに関する研究」と題する講演をそれぞれしていただきました。また全33件の講演発表があり、多くの方に参加頂きました。
イ. 地方講演会
2024年9月17日、第91回熊本八代講演会を熊本高等専門学校八代キャンパスにて開催いたしました。熊本県産業振興顧問 今村 徹様に「セミコン熊本の歴史的変革~急成長する熊本の半導体産業~」と題する特別講演をしていただきました。また全36件の講演発表があり、多くの方に参加頂きました。
翌18日には、見学会としまして九州電力㈱大平揚水発電所とルネサスエレクトロニクス㈱川尻工場を見学いたしました。
(4)啓蒙・啓発事業(講習会・セミナー、交流会等の開催)
の達成となりました。講習会・セミナー、継続教育プログラム(CPD)初級講座、及びフレッシュマンセミナーは例年どおり開催することができました。新「アフターヌーンセミナー」も全3回開催しています。コロナ禍で中断しておりました、特別会員交流会・分科会報告会の同時開催も行いました。
国際化事業として、2024年8月に、韓国流体機械学会(KSFM)との協力体制を構築し、12月の韓国流体機械学会の冬期講演会に本会も発表を実施いたしました。
(5)表彰事業
昨年5月17日の総会講演会表彰式において、ターボ機械協会論文賞2件、技術賞3件、および小宮研究助成金1件と畠山研究助成金1件をそれぞれ授与いたしました。
(6)会員サービス事業、他
正会員+学生会員数は2024年4月時点で876名でしたが、2025年3月時点では861名+トライアル会員4名に減少しています。一方、特別会員の数に関しては、145社から146社になりました。今後も、個人会員と特別会員各社にメリットを感じて頂ける施策を検討するのと、トライアル会員の方々に正会員になって頂くことが重要と考えます。
会費の納入や各種行事の出席管理を管理し、運営の効率化を図るために会員管理システム シクミネットの導入を完了し、会員情報の入力を依頼中です。会員の登録を進め,運営のスマート化を図っております。
【事業活動の概要】
一般社団法人ターボ機械協会(以下、本会)は1,000名近くの正会員、学生会員と約150社の特別会員を擁する、プロフェッショナル集団です。本会は、産官学が一体となって、新規技術の適用可能性の調査研究や情報共有を図ることを目的とした調査研究事業(分科会活動)、雑誌「ターボ機械」の発行、規格・規準の取り纏め、国際誌「International Journal of Fluids Machinery and Systems(IJFMS)」に対する編集協力などの出版事業、総会講演会・地方講演会・国際会議の開催などの集会事業、各種セミナーや交流会の開催をとおした啓蒙・啓発事業、畠山賞・小宮賞の贈呈などの表彰事業、および、会員にとって有益な情報を提供する会員サービス事業を主な事業として活動をしています。
本会の総会、理事会、講演会、セミナー、CPD講座、講習会、委員会・分科会などの事業活動は、従来通りの活動を継続しています。オンサイト開催を基本に、オンラインシステムも併用した運営を実施し参加者の増加に貢献しております。
予算に関して、当初予算では1,756千円を見込んでいた当期収支差額は約585千円の赤字となる見込みです。これは、個人会員受取会費の4,724千円(2024年度分)、962千円(2023年度分)の未回収、特別会員受取会費の未回収718千円、シンポジウム講習会費,出版会費の2,555千円の増収などの結果となります。個人会員の受取会費の回収は喫緊の課題であり早急な対策により収支の改善を検討します。本会の最大の懸案事項である会員数の減少に関しては、本年度当初の正会員+学生会員数876名に対して、年度末会員数は861名+トライアル会員数17名となっており、若干減少傾向にあります。会員増強に関しては、引き続きイノベーション推進委員会などで対策の協議を継続していきます。
本年度は、上記のように各種事業を予定通り実施できた結果、会費受け取りの遅延による財務の悪化と会員数減少の傾向をある程度緩和することができたと認識しております。
以下、項目別に2024年度の事業活動の概要を報告いたします。
(1)調査研究事業(委員会・分科会活動)
現在、協会には水力機械委員会の下に7分科会(水車分科会、キャビテーション研究分科会、ターボポンプ分科会、水力エネルギー分科会、ポンプ吸込水槽模型試験法の調査・研究分科会、海洋ターボ機械技術開発分科会、プロペラ分科会)、空気機械委員会の下に2分科会(可変速(VSD)モーター駆動回転機械の諸問題検討分科会、送風機・圧縮機の騒音と性能研究分科会)、蒸気機械委員会の下に1分科会(蒸気タービン技術向上分科会)が常設分科会それぞれ設置されています。これらの常設分科会は、水力機械、空気機械、および蒸気機械のそれぞれの機械に関連した調査研究や情報共有を図ることを主たる目的として活動していますが、総務理事会の下に設置されている、トライボロジー研究分科会、ロータダイナミクス研究分科会、生産技術研究分科会、過給エンジンシステム分科会および多領域ダイナミクス設計研究分科会の5つの分科会では、横串を通す基盤技術に関する情報共有を図っています。また、活発な活動を実施してきた流体性能の高精度予測と革新的流体設計分科会は2024年7月に最終成果報告書の提出で終了いたしましたが、その後継分科会としてターボ機械および船舶分野における次世代計算技術の実用化推進分科会が発足しました。また、カーボンニュートラル社会の実現のために早急に社会実装を実現する必要がある液体水素などを用いる流体機械、流体機器の課題解決、開発支援のために極低温流体基盤・応用技術研究分科会が発足し活発な活動を開始いたしました。ターボ機械に関するプロフェッショナル集団として、分科会活動を更に活性化して行くため、新設あるいは改編などの討議を継続して行きたいと考えています。
(2)出版事業
雑誌「ターボ機械」52巻第4号(2024年4月号発行)から53巻第3号(2025年3月発行)の12冊を編集・発行しました。
(3)集会事業
ア. 総会講演会
2024年5月17日、第90回総会講演会を早稲田大学西早稲田キャンパスにて開催いたしました。元当協会会長の加藤千幸先生(日本大学)に「ターボ機械のCFDの現状と今後の展望 ~40年余りの開発と応用の経験から~」と題する特別講演をしていただきました。
第35回 小宮助成金受賞者講演として、筑波大学の金川哲也先生により「気泡流中を伝わる圧力波の非線形発展を利用したポンプ内水管の保守管理のための基盤理論創成と技術開発」、第33回 畠山助成金受賞者講演として佐賀大学の木上洋一先生により「潮流発電用の往復流型集流装置付きタービンに関する研究」と題する講演をそれぞれしていただきました。また全33件の講演発表があり、多くの方に参加頂きました。
イ. 地方講演会
2024年9月17日、第91回熊本八代講演会を熊本高等専門学校八代キャンパスにて開催いたしました。熊本県産業振興顧問 今村 徹様に「セミコン熊本の歴史的変革~急成長する熊本の半導体産業~」と題する特別講演をしていただきました。また全36件の講演発表があり、多くの方に参加頂きました。
翌18日には、見学会としまして九州電力㈱大平揚水発電所とルネサスエレクトロニクス㈱川尻工場を見学いたしました。
(4)啓蒙・啓発事業(講習会・セミナー、交流会等の開催)
の達成となりました。講習会・セミナー、継続教育プログラム(CPD)初級講座、及びフレッシュマンセミナーは例年どおり開催することができました。新「アフターヌーンセミナー」も全3回開催しています。コロナ禍で中断しておりました、特別会員交流会・分科会報告会の同時開催も行いました。
国際化事業として、2024年8月に、韓国流体機械学会(KSFM)との協力体制を構築し、12月の韓国流体機械学会の冬期講演会に本会も発表を実施いたしました。
(5)表彰事業
昨年5月17日の総会講演会表彰式において、ターボ機械協会論文賞2件、技術賞3件、および小宮研究助成金1件と畠山研究助成金1件をそれぞれ授与いたしました。
(6)会員サービス事業、他
正会員+学生会員数は2024年4月時点で876名でしたが、2025年3月時点では861名+トライアル会員4名に減少しています。一方、特別会員の数に関しては、145社から146社になりました。今後も、個人会員と特別会員各社にメリットを感じて頂ける施策を検討するのと、トライアル会員の方々に正会員になって頂くことが重要と考えます。
会費の納入や各種行事の出席管理を管理し、運営の効率化を図るために会員管理システム シクミネットの導入を完了し、会員情報の入力を依頼中です。会員の登録を進め,運営のスマート化を図っております。
【行事等の開催記録】
| 行事種別 | 会合等の名称 | 開催日 | 開催場所 | 参加人数 |
| 通常総会 | 第14期 | 2024年5月17日 | 早稲田大学開催 | 76名 |
| 定例理事会 | 第1回 | 2024年5月17日 | 早稲田大学・Webex ハイブリッド開催 | 39名 |
| 第2回 | 2024年6月21日 | 日機装技術研究所・Webex ハイブリッド開催 | 40名 | |
| 第3回 | 2024年8月23日 | 荏原製作所・Webex ハイブリッド開催 |
33名 | |
| 第4回 | 2024年10月11日 | 早稲田大学・Webex ハイブリッド開催 | 37名 | |
| 第5回 | 2024年12月13日 | 荏原製作所・Webex ハイブリッド開催 | 36名 | |
| 第6回 | 2025年2月14日 | 早稲田大学・Webex ハイブリッド開催 | 32名 | |
| 第7回 | 2025年4月18日 | 日機装技術研究所・Webex ハイブリッド開催 | 38名 | |
| 講演会 | 第90回 総会講演会 | 2024年5月17日(金) | 早稲田大学 | 153名 |
| 第91回 熊本 八代講演会 | 2024年9月17日(火) | 熊本高等専門学校 | 85名 | |
| 特別会員交流会 | 特別会員交流会・分科会報告会 同時開催 | 2025年3月14日(金) | 早稲田大学 | 参加:80名 |
| 報告会 | ポスター展示:39機関 | |||
| Webinarシリーズ | 延期 | |||
| 語ろう会 | 第35回 語ろう会(関西地区) | 2024年5月24日(金)・25日(土) | 川崎重工業㈱神戸工場 | 8名 |
| セミナー | 第173回セミナー「水車」 | 2024年4月17日(水) | 早稲田大学・Webex ハイブリッド開催 | 43名 |
| 第174回セミナー「設備の計測とスマート化」 | 2024年6月7日(金) | 早稲田大学・Webex ハイブリッド開催 | 38名 | |
| 第37回 フレッシュマン・サマーセミナー | 2024年8月29日(木)・30日(金) | 大阪大学/Zoom ハイブリッド開催 | 61名 | |
| 第175回セミナー「ターボ機械システムの振動問題」 | 2024年9月27日(金) | 早稲田大学・Webex ハイブリッド開催 | 38名 | |
| 第176回セミナー「海外プラントにおけるターボ機械へのユーザー最新技術要求」 | 2024年11月8日(金) | 早稲田大学・Webex ハイブリッド開催 | 36名 | |
| 第177回セミナー「水素・アンモニア市場動向と回転機械への技術要求」 | 2025年1月17日(月) | 早稲田大学・Webex ハイブリッド開催 | 46名 | |
| 第178回セミナー「流体性能の高精度予測と革新的流体設計」 | 2025年3月17日(月) | 早稲田大学・Webex ハイブリッド開催 | 26名 | |
| CPD初級講座 | 第15回CPD初級講座:電送機・発電機 | 2024年4月24日(金) | 早稲田大学・Webex ハイブリッド開催 | 19名 |
| 第16回CPD初級講座:騒音 | 2024年6月13日(木) | 早稲田大学・Webex ハイブリッド開催 | 12名 | |
| 第17回CPD初級講座:すべり軸受 | 2024年7月25日(木) | 早稲田大学・Webex ハイブリッド開催 | 26名 | |
| 第18回CPD初級講座:ターボ機械の運転制御と特異現象 | 2024年10月15日(火) | 早稲田大学・Webex ハイブリッド開催 | 16名 | |
| 第10クール 第1回CPD初級講座:ターボ機械入門 |
2024年11月21日(木) | 早稲田大学・Webex ハイブリッド開催 | 32名 | |
| 第2回CPD初級講座:ポンプの水力設計入門 | 2024年12月5日(木) | 早稲田大学・Webex ハイブリッド開催 | 23名 | |
| 第3回CPD初級講座:ターボ機械の強度設計Ⅰ(概論) | 2025年1月22日(水) | 早稲田大学・Webex ハイブリッド開催 | 22名 | |
| 第4回CPD初級講座:ターボ機械の強度設計Ⅱ(材料力学、疲労強度) | 2025年1月23日(木) | 早稲田大学・Webex ハイブリッド開催 | 23名 | |
| 第5回CPD初級講座:金属材料 | 2025年2月25日(火) | 早稲田大学・Webex ハイブリッド開催 | 23名 | |
| 第6回CPD初級講座:腐食 | 2025年3月24日(月) | 早稲田大学・Webex ハイブリッド開催 | 20名 | |
| アフターヌーンセミナー | A1セミナー:ターボ機械のキャビテーション現象1 | 2024年12月12日(木) | W早稲田大学・Webex ハイブリッド開催 | 35名 |
| A2セミナー:ターボ機械のキャビテーション現象2 | 2024年12月17日(火) | Webex オンライン開催 | 36名 | |
| A3セミナー:世界の頂点を目指そう! | 2025年2月27日(木) | W早稲田大学・Webex ハイブリッド開催 | 48名 | |
| 新代議員懇談会 | 第15期 新代議員懇談会 | 開催中止 |
【行事等の開催回数】
| 行事等の種別 | 会合等の名称 | 開催回数 |
| 総会 | 通常総会 | 1回:ハイブリッド開催 |
| 理事会等 | 定例理事会 | 1回:ハイブリッド開催・6回:ハイブリッド開催 |
| 総務理事会 | 6回:ハイブリッド開催 | |
| 企画理事会(委員会を含む) | 6回:ハイブリッド開催 | |
| 編集理事会(委員会を含む) | 12回:(Webex開催) | |
| イノベーション推進委員会 | 6回:ハイブリッド開催 | |
| 委員会・分科会 | 水力機械委員会 | 1回 |
| 水車分科会 | 4回 | |
| キャビテーション研究分科会 | 3回 | |
| ターボポンプ分科会 | 3回 | |
| 水力エネルギー分科会 | 0回 | |
| ポンプ吸込水槽模型試験法の調査・研究分科会 | 1回 | |
| 海洋ターボ機械技術開発分科会 | 3回 | |
| プロペラ分科会 | 2回 | |
| 空気機械委員会 | 1回 | |
| 可変速(VFD)モーター駆動回転機械の諸問題検討分科会 | 1回 | |
| 送風機・圧縮機の騒音と性能研究分科会 | 2回 | |
| 蒸気機械委員会 | 2回 | |
| 蒸気タービン技術向上分科会 | 4回(内、幹事会2回) | |
| トライボロジー研究分科会 | 1回 | |
| ロータダイナミクス研究分科会 | 3回 | |
| 生産技術研究分科会 | 0回 | |
| 多領域ダイナミクス研究分科会 | 3回 | |
| 過給エンジンシステム分科会 | 0回 | |
| 極低温流体基板・応用技術研究分科会 | 4回 | |
| ターボ機械および船舶分野における次世代計算技術の実用化推進分科会 | 4回 | |
| 関西地区委員会 | 3回 | |
| 継続教育委員会 | 1回 | |
| 国際化委員会 | 状況に応じてメール審議を実施 | |
| 広報小委員会・拡大広報小委員会 | 0回 | |
| 若手委員会 | 0回 | |
| 表彰委員会・論文賞委員会 | 表彰委員会 | 1回(メール審議) |
| 論文賞審査委員会 | 1回(メール審議) | |
| 技術賞ヒアリング | 1回(Web審議) |